本文
多文化共生・やさしい日本語を使ってみませんか?
その「お知らせ」、伝えたい相手に本当に伝わっていますか?
大切な情報を外国人の方にしっかり伝えていくため、「やさしい日本語」をご活用ください!
在住外国人が増加・国籍多様化していく中、情報を伝える場合は、多言語で翻訳・通訳するほか、「やさしい日本語」を活用することが有効です。
「やさしい日本語」とは
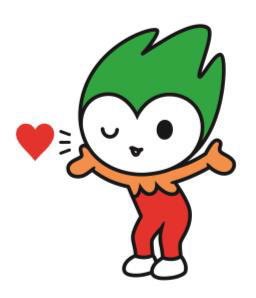 やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。日本語の持つ美しさや豊かさを軽視するものではなく、外国人、高齢者や障害のある人など、多くの人に日本語を使ってわかりやすく伝えようとするものです。
やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。日本語の持つ美しさや豊かさを軽視するものではなく、外国人、高齢者や障害のある人など、多くの人に日本語を使ってわかりやすく伝えようとするものです。
やさしい日本語の歴史は、1995年の阪神・淡路大震災に遡ります。この震災のとき、日本人の死傷者は約1%でしたが、外国人の死傷者は2%以上でした。これ以降、外国人に対しても迅速に災害などの情報伝達を行う手段として取組が始まり、その後、新潟県中越地震(2004年)や東日本大震災(2011年)を経て、災害時のやさしい日本語での発信の取組が全国に広がりました。
一方、平時のやさしい日本語での情報発信も、2000年代に入ってから、地方公共団体や国際交流協会で始まっています。近年では、外国人観光客とのコミュニケーションや、外国人住民と日本人住民の交流を促進する手段としてやさしい日本語を活用した取組も進んでいます。
(出典:「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(出入国在留管理庁、文化庁))
本県における取組
(1)山口県国際交流協会と連携した取組
やさしい日本語の普及啓発に向け、「やさしい日本語講座」を山口県国際交流協会や市町との協働により実施しています。
令和4年度の取組
- 地域日本語教育推進事業(文化庁:「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用・県国際交流協会へ委託)として、やさしい日本語講座を開催しました。
- 全県:令和4年6月4日(土曜日)
- 下関市:令和4年10月29日(土曜日)
- 下松市:令和4年11月5日(土曜日)
- 行政職員・関係団体職員向け:令和4年10月20日(木曜日)
- 詳細は、地域日本語教育教育の推進についてをご参照ください。
令和3年度の取組
- 地域日本語教育推進事業(文化庁:「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用・県国際交流協会へ委託)として、全県(オンライン)、行政職員向け(オンライン)、長門市(オンライン)の計3回、やさしい日本語講座を開催しました。
- 全県:令和3年5月29日(土曜日)
- 行政職員向け:令和3年7月14日(水曜日)
- 長門市:令和4年1月22日(土曜日)
(2)防災・減災に向けた取組
 災害が発生した際の被害を最小限にするため、災害の特徴や避難方法、日頃からの備えなどについて掲載した「防災ハンドブック(やさしい日本語版)(PDF:7.11MB)」を作成しました。
災害が発生した際の被害を最小限にするため、災害の特徴や避難方法、日頃からの備えなどについて掲載した「防災ハンドブック(やさしい日本語版)(PDF:7.11MB)」を作成しました。
なお、防災ハンドブックは英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語の各版もあります。詳しくは外国人住民のための防災ハンドブック・緊急カードをご覧ください。
「やさしい日本語」を使ってみましょう!
「やさしい日本語」に絶対的な正解はありません。
相手にわかりやすく伝えていくか…言い方を変えてみたり、多くの事例や時にはイラストも交えたり。
外国人の方と接する機会はもちろん、普段からまずは身の回りの言葉の「やさしい日本語」化に、楽しみながらチャレンジしてみてください!
「やさしい日本語」関連情報
やさしい日本語の理解・活用に便利な資料やホームページをご紹介しています。
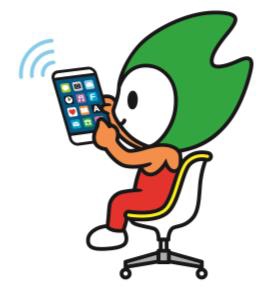
- 在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン等
在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインの概要 (PDF:256KB)
在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン (PDF:1.66MB)
出入国在留管理庁と文化庁が、共生社会実現に向けたやさしい日本語の活用を促進するため、多文化共生や日本語の有識者、外国人を支援する団体の関係者などを集めた在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインに関する有識者会議を開催し、やさしい日本語を活用している地方公共団体や外国人の意見を聞いて作成したものです。(中略)
別冊のやさしい日本語書き換え例では、日本語をやさしい日本語に変換する際の一例を掲載しています。
(出典:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html))
- 公益財団法人山口県国際交流協会ホームページ「多文化共生・やさしい日本語」<外部リンク>
「やさしい日本語の例」や「やさしい日本語のポイント」、「関連リンク」などの情報が掲載されています。

